
 【L】4年前の失敗を思い出し、息切れする前に立ち止まり、足が上がらなくなる前に立ち止まり。
【L】4年前の失敗を思い出し、息切れする前に立ち止まり、足が上がらなくなる前に立ち止まり。そして、30分に一度は荷物をおろして休憩。
この繰り返しで高度を稼いでいきます。
【R】4年前は2時間登って1歩も上がれなくなりました。
この木のベンチは記憶にありません。
まだ登りはじめて1時間も経っていないのに。
4年前、ほとんど上がってなかったということです。

 【L】わかりづらいですが、大きなヒキガエルです。
【L】わかりづらいですが、大きなヒキガエルです。実は4年前のあのときも、このくらいのカエルに会いました。
笠新道の主なのでしょうか。
カエルさん、今回はどうか通過させてくださいよ。
そのときは、じっとこちらをみつめていたのですが、今回は逃げるようにいなくなりました。
【R】明るくなってくると同時に雨があがってきました。
雨具を脱いで、ザックにしまいました。

 【L】標高1700m。
【L】標高1700m。こういう標識も今回初めて目にしました。
笠新道入口が1350mですから、標高にして350m上がってきたことになります。
【R】樹林帯が少しずつ開けてきて、木々の間から槍ヶ岳が見えてきました。

 【L】壊れてますが、1800m。
【L】壊れてますが、1800m。ガイドブックに書いてあったように、おもしろいように高度が稼げます。
【R】まわりの木々も背が低くなり、展望が開けてきました。

 【L】1920m。
【L】1920m。中途半端な高さだなあと思ったら、中間点でした。
ここまで入口から2時間。
杓子平までコースタイムが4時間半だから、早いペースじゃないか。
と思ったのが甘かったです。
ここからがほんとに長かったです。
【R】木々の背は低くなってきたけど、まだこんなに大きな木が。
まるで登山道のゲートのようです。

 【L】立ち止まったときに目に入ったドラゴンのような木。
【L】立ち止まったときに目に入ったドラゴンのような木。霧の中で不気味に見えました。
【R】ほんとに高い木が少なくなって、まわりが開けてきました。1

 【L】でも、霧が深く、下の方はほとんど見えませんでした。
【L】でも、霧が深く、下の方はほとんど見えませんでした。【R】つづら折りも崩れてきて、ちょっと立ち止まるペースが取りづらくなってきました。

 【L】「一望できます」とありますが、霧で真白で何も見えませんでした。
【L】「一望できます」とありますが、霧で真白で何も見えませんでした。【R】9月に山に登ると必ず咲いている、山ならではの大きなアザミです。

 【L】登山道が崩れて大きなガレ場というか涸れた沢越えというか・・
【L】登山道が崩れて大きなガレ場というか涸れた沢越えというか・・よくこういうところで道迷いをしてしまします。
慎重にペンキマークや赤リボンを探します。
【R】リンドウの一種でしょうか。
雨上がりなので、葉についた水玉がきれいです。

 【L】下ばかり見て歩いていると、このようなペンキマークを見落とします。
【L】下ばかり見て歩いていると、このようなペンキマークを見落とします。これを見落とすと、真っ直ぐ行ってしまいそうな道でした。
【R】標高が上がるに連れ、青空が広がってきました。

 【L】標高2200m付近です。
【L】標高2200m付近です。穂高の稜線が目の前に現れました。
霧と木々だけ見てきたので、「登ってきた」という感じです。
さきほどまでの霧の世界はもう目の下です。
【R】南に目をやると、焼岳とその右に乗鞍が。
この2つはどこからみても、それとわかります。

 【L】どこからみてもわかるといえば、もちろん槍ヶ岳。
【L】どこからみてもわかるといえば、もちろん槍ヶ岳。ここで試しに携帯の電源を入れたら、アンテナが立ちました。
時刻は8時過ぎ。
下界のみなさんに、1本目のメールを送りました。
【R】上を見ると、青空と山の境目が。
あの先が杓子平でしょうか。

 【L】写真だとあっという間ですが、ここまでが長かったのです。
【L】写真だとあっという間ですが、ここまでが長かったのです。写真も撮り忘れるほど、登ることに集中していました。
【R】そしてここからは、今日の目的地、笠ヶ岳の山容がはっきりと見えてきました。

 【L】とはいえ、そこにまっすぐ行ける道はなく、まずは、笠ヶ岳から少し右に目をやったところに見えるこの山(抜戸岳))を目指します。
【L】とはいえ、そこにまっすぐ行ける道はなく、まずは、笠ヶ岳から少し右に目をやったところに見えるこの山(抜戸岳))を目指します。【R】今までの急登はしばらくひと休み。
なだらかな高原歩きを楽しめそうです。

 【L】と思ったのも、つかの間。
【L】と思ったのも、つかの間。すぐにまた急登が始まりました。
【R】さきほどはつぼみだったこのリンドウの一種も、ここでは日当たりがいいのか、咲いてました。

 【L】笠新道とは違って、先が見えているだけに、キツイ登りです。
【L】笠新道とは違って、先が見えているだけに、キツイ登りです。笠新道でのダメージが響いて、思うように足が上がりません。
【R】ずっと見えていた笠ヶ岳とも一旦お別れです。

 【L】これもこの時期目にする、チングルマの綿毛。
【L】これもこの時期目にする、チングルマの綿毛。【R】まとまって咲いてました。

 【L】標高が上がってきたので、先ほどまでは見えなかった御嶽山が、乗鞍の先に見えてきました。
【L】標高が上がってきたので、先ほどまでは見えなかった御嶽山が、乗鞍の先に見えてきました。【R】これは後ほど同行していただいた方に教えていただいたのですが、ウメバチソウだそうです。

 【L】これも同じ方に教えていただきましたが、ハハコグサだとか。
【L】これも同じ方に教えていただきましたが、ハハコグサだとか。【R】急登を登りつめ、稜線に出ました。
ここまでほぼ同じペースで歩いてきた3人が一同に会し、自己紹介しながらお昼を摂りました。

 【L】そこから少し下りると、稜線分岐に出ました。
【L】そこから少し下りると、稜線分岐に出ました。標識の先には、裏銀座の山々が。
【R】笠ヶ岳へ続く稜線です。
笠ヶ岳はガスに隠れてますが、ここからはアップダウンもほとんどなく、快適な稜線歩きを楽しめそうです。

 【L】標高が高いから、木の根もなく、歩きやすい道が続きます。
【L】標高が高いから、木の根もなく、歩きやすい道が続きます。【R】このあたりからさきほどお昼を一緒に食べたお二人に追いつき、同行させていただくことにしました。

 【L】前に見えてきたのは、抜戸岩。
【L】前に見えてきたのは、抜戸岩。【R】ほんとに岩の間を抜けていきます。

 【L】ガレ場の上に今夜泊まる笠ヶ岳山荘が見えてきました。
【L】ガレ場の上に今夜泊まる笠ヶ岳山荘が見えてきました。このあたりがテン場ですが、水を汲むには山荘まで往復しなければならないようです。
【R】その右にはガスに隠れてますが、小さな小笠。

 【L】だんだんと山荘が近づいてきます。
【L】だんだんと山荘が近づいてきます。【R】大きな石の上をペンキマークに沿って歩くので、なかなか近づきません。

 【L】山荘から見上げた笠ヶ岳。
【L】山荘から見上げた笠ヶ岳。ここで荷物をデポして、空身になって山頂を目指します。
【R】30分ほどで山頂に着きましたが、ここが最高点ではなかったようです。
この祠、あとで立ち寄ります。

 【L】そこからちょっと先に行ったところが、ほんとの頂上のようです。
【L】そこからちょっと先に行ったところが、ほんとの頂上のようです。【R】笠ヶ岳山頂です。
今回は、山頂に立ったことよりも、あの笠新道を踏破したことに達成感を感じます。
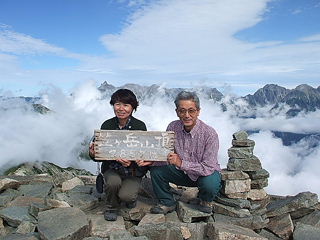
 【L】稜線分岐から同行させていただいたお二人。
【L】稜線分岐から同行させていただいたお二人。左が翌日も途中まで同行していただいたT子さん、右がRSさん。
どちらも愛知県から来られた方々です。
【R】私も学生時代4年間は愛知県。
今回は愛知県つながりの3人でした。

 【L】笠ヶ岳山頂の三角点を踏みました。
【L】笠ヶ岳山頂の三角点を踏みました。【R】山荘で買ってきたコカコーラ。
山頂で飲む炭酸は最高です。
中学のとき林間学校で蓼科山に登りましたが、山頂に立ったのは5人だけ。
引率の先生は1本200円のコーラを全員におごってくれました。
それ以来、山のコーラはビールと同じくらい、おいしくいただいてます。

 【L】さきほど通過した祠です。
【L】さきほど通過した祠です。中には笠ヶ岳を再興した播隆さんが奉納したものでしょうか、仏像が安置されていました。
【R】さて、山荘に下りて、夕食までくつろぎタイムです。
ほんの1時間か2時間ですが、この時間がとても大切です。
なので、私は遅くても15時過ぎには小屋に着きたいのです。

 【L】平日にもかかわらず、小屋は結構な賑わいでした。
【L】平日にもかかわらず、小屋は結構な賑わいでした。小屋番さんに聞くと、それでも定員の半分くらいだとか。
まあ定員いっぱいになったら、寿司詰め状態でしょうからね。
【R】夕食は17時から。
昨日の小屋はともかく、こんな山の上でもそばが出たことに驚きです。

 【L】メインのおかず。
【L】メインのおかず。山小屋としては豪華です。
というか、最近、小屋の食事はどこも豪華です。
【R】食後、小屋の前のテラスから山を眺めました。
今日歩いてきた稜線。明日またここを歩いていきます。
そしてその先には槍ヶ岳が。

 【L】穂高の稜線も雲の上に浮かんでます。
【L】穂高の稜線も雲の上に浮かんでます。【R】槍をバックに撮ってもらいました。
この後、後ろのガスに笠ヶ岳の影が映っていたので、そこにいた人たちはブロッケンを期待しました。
「誰か小笠に登ればブロッケンが見えるかも」誰かそういうことを言いだしました。
そしたら、ちょうど出てきたさっきのT子さん、小屋のサンダル履きで小笠に駆け上って両手を大きく振りました。
残念ながらブロッケンは見えなかったけど、その行動力に拍手しました。

 【L】テラスとは逆側の西側にある石畳。
【L】テラスとは逆側の西側にある石畳。結構大きなものもあるので、どうやって敷いたのか不思議でした。
【R】ああ、この重機を使ったのかもしれないです。
でも、この重機、どうやってこの山の上に運んできたんだろう。
新たな疑問が。
 白山方面に夕日が沈んでいきました。
白山方面に夕日が沈んでいきました。明日もいい天気でしょう。
笠新道から、笠ヶ岳,双六岳,三俣蓮華岳,鷲羽岳 メニューへ戻る